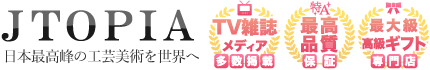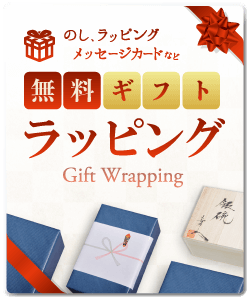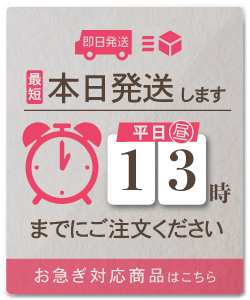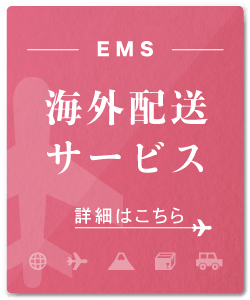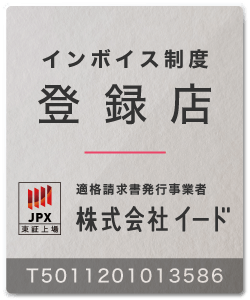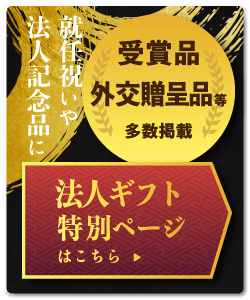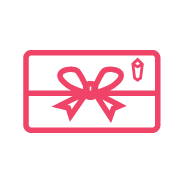津軽の馬鹿塗り? 津軽塗の由来と魅力とは
国の伝統工芸品に選出されている津軽塗の特徴とは?
津軽塗は津軽海峡で有名な青森県の漆器で、国の重要無形文化財にも指定されています。江戸時代に弘前藩の藩主が、津軽の産業を育成するために全国各地から職人を集めて始めたと言われます。津軽塗の土台には、ヒバという青森県産の木材が使用されています。
その特徴は工程の多さにあり、40回以上の工程を繰り返して作られます。津軽塗には4種類の技法がありますが、そのどれも漆を何十回も塗り重ね、研磨仕上げを施していくのです。その分、完成するまでに日数がかかることから「津軽の馬鹿塗り」とも呼ばれることもあります。馬鹿丁寧に何度も何度も工程を踏まなければならないことから、そう呼ばれるようになりました。
300年前に生まれた技法は現在も脈々と受け継がれており、幾層もの漆が奥行きと力強さが感じられる何とも言えない美しさを生み出します。津軽塗の美しさは世界的にも高く評価されていて、明治時代に行われたウィーン万国博覧会では賞を受賞しました。
津軽塗の代表的な4種類
津軽塗の代表的な4種類の技法には、紋紗塗(もんしゃぬり)・七々子塗(ななこぬり)・錦塗(にしきぬり)・唐塗(からぬり)があります。
紋紗塗(もんしゃぬり)は、黒漆の模様に紗と呼ばれる炭粉を撒いて研ぎ出して磨いたものをいいます。艶消しの黒地に艶のある黒漆が浮き出てくる技法で、洗練された渋みが感じられます。研ぎ出し技法の中では非常に独特なもので、津軽塗ならではといえるでしょう。
七々子塗(ななこぬり)は、模様をつけるために菜の花の種を撒きつける技法になります。菜の花の種が生み出す模様が魚の卵のように見えることから、魚の卵を表す言葉の「七々子」と呼ばれるようになりました。江戸小紋風の塗りで、粋な印象を与えてくれます。
錦塗(にしきぬり)は、七々子塗(ななこぬり)を塗りを基本としている豪華な塗りの技法の一種になります。七々子地に黒漆で唐草をデザインしたり、菱形や稲妻を描いて銀粉を撒いたりします。金や銀があしらわれた蒔絵をイメージさせる技法で、津軽塗の中でも特に高度な技術が必要です。そのため製作できる職人は限られており、その漆器は希少価値があります。豪華絢爛で華やかな漆器といえます。
唐塗(からぬり)は津軽塗を代表する最もオーソドックスな技法で、数も一番多く生産されています。唐塗(からぬり)独特の複雑な斑点模様が特徴で、卵白を入れた黒漆を仕掛けベラを使って斑点模様をつけていきます。その上に色漆を塗り重ねて、研磨すると独特の模様が現れる仕組みです。作り始めてから完成するまでに最低でも2か月程度かかると言われます。
津軽塗の漆器には、箸・お椀・銘々皿・お盆・菓子器・なつめ・重箱・ぐい呑み等があります。箸などは食事の際に毎回使用するもので、日常の生活に深く根付いています。清潔で扱いやすく、汚れが付きにくいというメリットもあります。津軽塗は漆器の中でも手触りが良く、飽きの来ない普遍的な美しさがあります。